映画『土を喰らう十二ヵ月』インタビュー
映画『土を喰らう十二ヵ月』は白馬の廃集落で撮影されました。映画づくりは古民家を改装し、畑を耕し、野菜を育てることからはじまりました。1年半もの時をかけ、本物の食材を使い、本当に料理をしながら、二十四節気に寄り添って撮影は進み、そこには長野の風土が幾重にも織り込まれています。監督の中江裕司さんと料理を担当した土井善晴さんに映画のことや長野とのつながりについてお聞きしました。

「白馬の風景が、主人公の人物像に肉付けしてくれました」=監督:中江裕司さん

白馬の廃集落と北アルプスとの出会い
映画の原案である水上勉さんのエッセイ『土を喰ふ日々』は軽井沢で書かれた本ですから、長野で撮ること、そして雪があることがロケ地の条件でした。ようやく見つけたのが白馬の菅(すげ)という廃集落です。現地を確認しに行った際は、膝まである雪のなか、除雪されていない道をビショビショになって進みました。
ようやく茅葺き屋根の家にたどり着いたとき、曇っていた空が晴れてきて、北アルプスがバーンと現れた。太陽がさして、祝福されているようでした。そのときに「ツトムは、この風景があるから、ここに住んだのだな」と思えたんです。沢田研二さん演じる主人公ツトムが北アルプスを愛する人だと、風景が人物像に肉付けしてくれました。

土井善晴さんに引き受けてもらうまで
土井善晴さんに料理をお願いするため、最初にお訪ねした時は「みなさんはどのレベルで考えているのですか」と言われてしまい、出直しました(苦笑)。
原案を読み返し、ツトムと料理の関係性を整理して、もう一度ご説明しに行ったけど、まだやるとおっしゃらない。「伊賀の福森雅武さんという陶工がいるから、そこの台所を見ておいで」と返されました。
それを機に福森さんのドキュメンタリー※を1年にわたって撮ることになり、映画を撮りながら伊賀にも通っていました。
土井さんは何度もやりとりするうちに真剣に映画に向き合ってくださるようになり、僕自身の準備も整っていったのだと思います。
※NHK BSプレミアム『圡楽さんの日日』
ツトム像を表す器を求めて東奔西走
土井さんには「料理は何とかなるものだから大丈夫。大事なのは器ですよ」と言われました。「何に盛るか、そこに(使う)人間があらわれる」と。僕は沖縄の映画館「桜坂劇場」を経営して、そこにある店で〝やちむん〟などを買いつけているので、器のことは多少わかっているつもりでしたが、ハードル高いですよ(笑)。
ツトムは違和感のあるものは使わないし、高いものをそろえる人でもない。そんなことを念頭に、沖縄の松田米司さんやアンパル陶房、松江の津田堅司くんなど、いろいろな方にお願いして映画のための器を集めました。
ツトムの飯碗は、福森さんの私物の逆根来塗りの椀をお借りして、松たか子さん演じる真知子のためにツトムがお抹茶を点てるシーンでは、土井さんの私物の器を使いました。どんな場面で、どの器に盛るか、確認しながら一つひとつの器を決めていきました

畑は料理ありき、山菜は山ありき
季節や場面を象徴する料理を想定してから、畑で育てる作物を決めました。家の前に畑を作るために、熊笹を伐採して、根っこや石を取り除き、撮影時に収穫できるよう逆算して種をまいて、半年がかりで開墾しました。
助監督とスタッフが撮影開始の半年前から白馬に住み込み、菅の手前にある野平地区の下川さんの指導も受けながら畑の世話をしました。助監督が農家の娘なので、妥協はなかった。おかげで収穫のシーンは、すべて自前の畑で撮影できました。
山菜は、土井さんが「長野はその時々にいろいろあるから大丈夫」とおっしゃる。そのとおりなんですが、撮るほうは山菜に合わせて準備をしないといけないから大変です。でも、映画の都合で嘘をつくことは、この映画ではやめよう、本物の食材を使い、本当に料理しようと心がけました。
お通夜のシーンを支えた長野の人たち
奈良岡朋子さんが演じるツトムの義母チエさんのお通夜のシーンは原案にはありません。長野の家庭料理である、なすの油味噌を作ることにしたのは土井さんのアイデアです。熱したフライパンになすをジャッと入れる。「その音がチエさんに届いて供養になる」と土井さんがおっしゃって、素晴らしい考えだなと思いました。
弔問客はオーディションで選ばれた長野の方です。セリフはディスカッションしながら北信(※長野県の地域区分で北部地方を指す)らしい言葉に置き換えてもらい、一緒に作っていきました。言葉は大事にしたかった。僕は沖縄で映画を撮ってきたので、本土の人が沖縄でおかしな言葉づかいで撮っているのが気に入らないわけです。長野の人に、そう思ってもらいたくなかった。さて、うまくいっているでしょうか。(談)

<中江裕司(なかえ・ゆうじ)>
映画監督、株式会社クランク代表取締役社長。1960年、京都府生まれ。琉球大学入学時に沖縄に移住。在学中から映画を撮りはじめ、92年『パイナップルツアーズ』でプロデビュー。92年『ナビィの恋』、99年『ホテル・ハイビスカス』が全国的にヒット。映画を製作しながら那覇市の映画館「桜坂劇場」を再興し、経営している。
「人間本意ではなく、自然のなかでできることを考え続けました」=料理担当:土井善晴さん
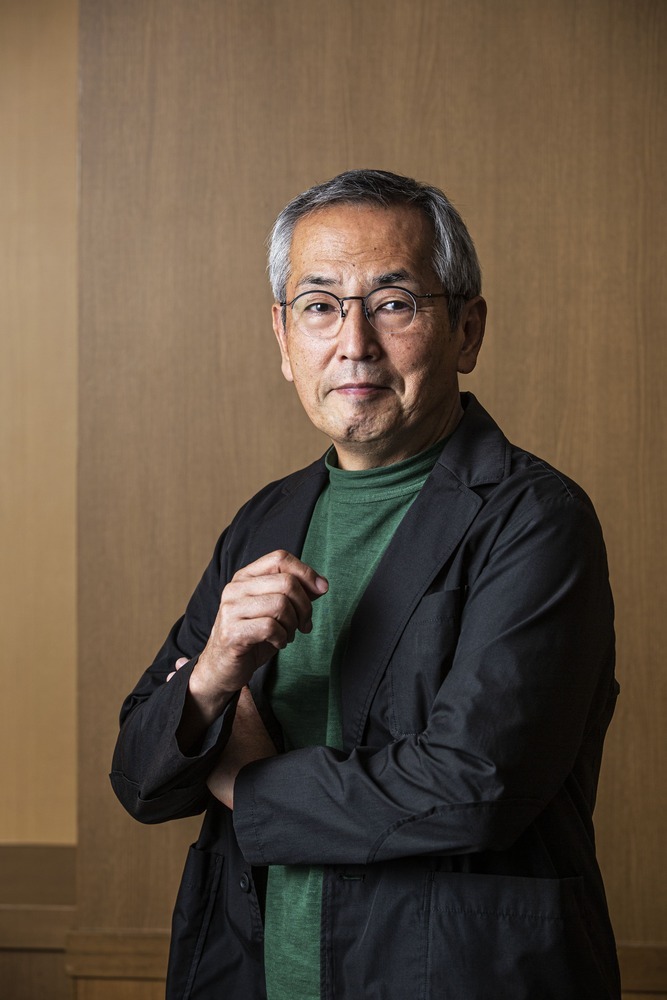
自然のなかでできることを考え続けた
中江監督から映画の料理を頼まれても、最初は問い返すばかり。「何を料理するか」は場があって人がいて、おのずと決まってくることですから、ロケ地の白馬という土地が基準になります。すべてその土地からはじまると考えていました。
人間は、おいしいものを食べればそういう顔になりますから。言葉はいりません。おいしいが前提です。たとえば筍は、水煮なら1年中あるけど、それを使ったら若竹煮にはならない。美しさも楽しさもない、意味がない。本当の料理を作らないと何も映らないと思うんです。だから、1年以上かかると監督に話しました。
台本に登場するのは、私が原作で読んだ水上勉さんではなく、監督が作り上げた現代のツトムだったので、料理が卓越したということではなく、監督や私と同年代の身近なひとりの男性作家が山にいるというイメージを考えました。
不慣れな男性が一生懸命、包丁を握るのは美しい。その手が重要なんですね。優れた技術が必ずしもおいしさにつながるものではないのです。大事なのは食材にまっすぐ向き合うこと。ツトムがどんな料理をして、どんな器に盛るか。その瞬間にどんな態度がふさわしいか、食材と人間の関係がどうあるべきかを考える。それが映画での私の仕事でした。

長野との関わりと映画の協力者
私と長野の関わりは29歳の頃、小布施で栗菓子屋さんの和食店の開発に携わったのが最初です。初夏の山をドライブしていたら、山ウドを採っているおじいさんに出会い、採れたてを食べさせてもらった。そのおいしさに頭を殴られるような衝撃を受け、本当の食材を何にも知らないことに気付きました。
それ以後も、善光寺門前の酒蔵でレストランの開発に携わり、長野には30年以上、毎月通いました。味噌マイスターの雲田寛さん(故人)には発酵学を教わり、春、初夏、秋と山に入り、映画でお世話になる堀米良男さんとも毎年のようにご一緒しています。堀米さんは、山で目に見えない水の流れを読むような人。中江監督とも山でご一緒しました。 今回、山菜などの食材は堀米さんご夫婦が協力してくださったんです。堀米のお母さん(奥さん)が作る干し柿は見事で、その干し柿も出てきます。
沢田研二さんと松たか子さんのこと
お料理のシーンは、沢田研二さんご自身でやっていらっしゃいます。演じるツトムがぬか漬けに手を入れるシーンで、沢田さんは「このぬか床、ちょっとかたいね」とおっしゃった。それだけで普段からいろいろされているのがわかります。
ツトムの恋人、真知子を演じる松たか子さんは、普段お料理をされているとすぐにわかりました。ごまをするシーンはあんまり上手だから、真知子がそれでは困るので、すりこぎの普通は持たないでしょうところを持ってもらいました。うまいこと下手になさる。おふたりとも普通にちゃんと生活されている方だと思いました。
美意識が働く撮影現場
結局、本番のお料理は1回しか作りませんでした。できあがったものを盛り付けて、食べるシーンまでひと息に撮るんです。監督が演出的に止めることもありません。ご飯が炊き上がるシーンでも、炊き上がったご飯の蓋を取るのは本番でやるので、本当の湯気が映ります。監督はじめスタッフ全員、お膳立てをしっかり整えて、緊張感がありました。
「こちらの角度から撮ったら、お料理のもっといい表情が見える」と監督に進言しても、「映画では、そうじゃないんです」と。映画は、料理番組と違って観る人の感性にゆだねてしまうんですね。だから2時間弱でもひとりの人間の人生が描ける。そんなこともこの映画を通して知ることができました。

この映画が示す本当の豊かさとは
毎日、料理をして食べること、そのくり返しが生活です。くり返しだからこそ、新しい発見があるんです。そこに気づくことが、かけがえのない喜びになり、人間は十分に生き生きとしていられる。それを知らないと、リタイアした後、なんとも寂しい生活になってしまうんです。仕事をしてないと何もすることがないというのでは、しんどいと思いますよ。
それを、ツトムは都会とはまったく違う価値観のなかに身を置くことで、人生を振り返りながら気付いていくのです。それがじつは現代社会が失ってしまった本当の意味での豊かさ、自分がなぜ生きているのか、そんなことにまでつながっている、いい映画だと思います。(談)

<土井善晴(どい・よしはる)>
料理研究家、十文字学園女子大学招聘教授、東京大学先端科学研究センター客員研究員など。1957年、大阪府生まれ。スイス、フランス、大阪で料理を修業し、土井勝料理学校勤務を経て、92年に「おいしいもの研究所」設立。各メディアを通して家庭料理の本質を伝える。著書に『一汁一菜でよいという提案』(新潮社)など多数。
撮影:宮崎純一(中江裕司さん)、三田村 優(土井善晴さん)、取材・文・編集:山口美緒・塚田結子(編集室いとぐち)、©️2022『土を喰らう十二ヵ月』製作委員会
閲覧に基づくおすすめ記事



